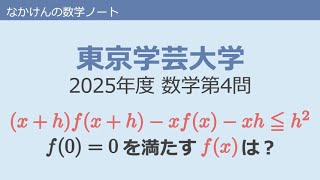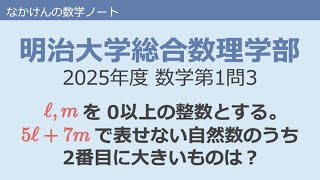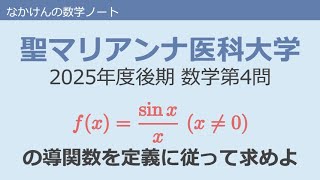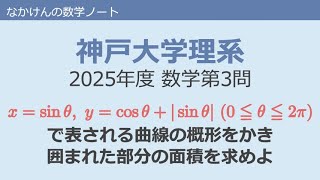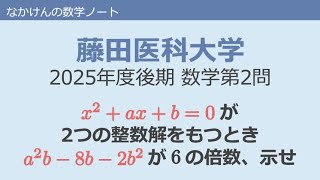京都大学 理学部特色入試 2020年度 第3問 解説
(2019年11月に行われた特色入試の問題です。2020年に行われた特色入試の問題はこちら)
問題編
問題
整数 $k,n$ は $0\leqq k\lt n$ を満たすとする。以下の設問に答えよ。
(1) $f(x)=x^n$, $g(x)=x^k$ とする。 $1\leqq x\lt y$ に対して、次の不等式が成り立つことを示せ。\[ \left| \frac{g(x)-g(y)}{f(x)-f(y)} \right| \lt\dfrac{1}{x} \]
(2) $f(x)$, $g(x)$ を実数係数の整式で、 $f(x)$ の次数を $n$ とし、 $g(x)$ の次数を $k$ 以下とする。 $f(x_0)$ が整数となるすべての実数 $x_0$ に対して $g(x_0)$ も整数となるとき、 $g(x)$ は $x$ によらず一定の整数値をとることを示せ。
考え方
(1)は具体的な関数が与えられているので、頑張って変形します。
(2)は、(1)を使いますが、少し使い方が難しいです。(1)では、 $x$ が大きいときには、 $x^k$ の差は $x^n$ の差に比べてずっと小さくなる、ということを表しています。このことから、 $g(x)$ の変化について何か言えないか考えてみましょう。
解答編
問題
整数 $k,n$ は $0\leqq k\lt n$ を満たすとする。以下の設問に答えよ。
(1) $f(x)=x^n$, $g(x)=x^k$ とする。 $1\leqq x\lt y$ に対して、次の不等式が成り立つことを示せ。\[ \left| \frac{g(x)-g(y)}{f(x)-f(y)} \right| \lt\dfrac{1}{x} \]
解答
$k=0$ のときは、 $g(x)-g(y)=0$ なので、問題文にある不等式はつねに成り立つ。よって、以下では、 $k$ が正の場合を考える。
$m$ を正の整数とする。\[ \frac{x^m-y^m}{x^{m+1}-y^{m+1} } \]の分母と分子をそれぞれ因数分解をして $x-y$ で割ると
\begin{eqnarray}
& &
\frac{x^m-y^m}{x^{m+1}-y^{m+1} } \\[5pt]
&=&
\frac{x^{m-1}+x^{m-2}y+x^{m-3}y^2+\cdots+xy^{m-2}+y^{m-1} }{x^{m}+x^{m-1}y+x^{m-2}y^2+\cdots+x^2y^{m-2}+xy^{m-1}+y^{m} } \\[5pt]
\end{eqnarray}となる( $m=1$ のときは、分子は $1$ )。ここで、分母から、分子に $x$ を掛けたものを引くと
\begin{eqnarray}
& &
(x^{m}+x^{m-1}y+x^{m-2}y^2+\cdots+x^2y^{m-2}+xy^{m-1}+y^{m}) \\
& & -x(x^{m-1}+x^{m-2}y+x^{m-3}y^2+\cdots+xy^{m-2}+y^{m-1}) \\[5pt]
&=& y^{m}
\end{eqnarray}となる。 $y$ は正なのでこの値は正である。また、 $x$ も正なので、以上のことから、任意の正の整数 $m$ に対して\[ \frac{x^m-y^m}{x^{m+1}-y^{m+1} } \lt \frac{1}{x} \]が成り立つ。
このことから、
\begin{eqnarray}
& &
\left| \frac{g(x)-g(y)}{f(x)-f(y)} \right| \\[5pt]
&=&
\frac{x^k-y^k}{x^n-y^n} \\[5pt]
&=&
\frac{x^k-y^k}{x^{k+1}-y^{k+1} } \cdot \frac{x^{k+1}-y^{k+1} }{x^{k+2}-y^{k+2} } \cdots \frac{x^{n-1}-y^{n-1} }{x^{n}-y^{n} } \\[5pt]
&\lt&
\left(\frac{1}{x}\right)^{n-k} \\[5pt]
&\leqq&
\frac{1}{x} \\[5pt]
\end{eqnarray}となる。
(1)終
解答編 つづき
問題
(2) $f(x)$, $g(x)$ を実数係数の整式で、 $f(x)$ の次数を $n$ とし、 $g(x)$ の次数を $k$ 以下とする。 $f(x_0)$ が整数となるすべての実数 $x_0$ に対して $g(x_0)$ も整数となるとき、 $g(x)$ は $x$ によらず一定の整数値をとることを示せ。
解答
$f(x)$ は $n$ 次の整式なので、 $x\to\infty$ のときに $|f(x)|\to\infty$ である。 $f(x)\to -\infty$ のときは $-f(x)$ を考えることにより、 $f(x)\to\infty$ としてよい。
$f(x)$ の極値は高々 $n-1$ 回なので、 $f(x)$ はある値から先は狭義単調増加となる。そのため、十分大きな整数 $A_0$ をとれば、「整数 $A$ が $A_0$ 以上なら $f(x_{A})=A$ となる実数 $x_A$ が存在する」ようにできる。なお、 $f(x)$ はある値から先では狭義単調増加だから、 $x_A\lt x_{A+1}$ となるようにとれる。また、 $A\to\infty$ なら $x_A\to\infty$ となる。
\[ f(x)=\sum_{i=0}^n a_i x^i \]とおく。ただし、 $a_n\ne 0$ とする。また、係数の絶対値のうち、一番大きいものを $a_{\max}$ とする。 $A$ を $A_0$ 以上の整数とすると
\begin{eqnarray}
& &
\left| \frac{\left(f(x_{A})-a_n x_{A}^n\right) -\left(f(x_{A+1})-a_n x_{A+1}^n\right)}{a_n x_{A}^n-a_n x_{A+1}^n} \right| \\[5pt]
&\leqq&
\frac{\displaystyle \sum_{i=0}^{n-1} |a_i| |x_{A}^i -x_{A+1}^i|}{|a_n| |x_{A}^n-x_{A+1}^n|} \\[5pt]
&\leqq&
\frac{|a_{\max}|}{|a_n|} \sum_{i=0}^{n-1} \left| \frac{x_{A}^i -x_{A+1}^i}{x_{A}^n-x_{A+1}^n} \right| \\[5pt]
&\leqq&
\frac{|a_{\max}|}{|a_n|} \cdot \frac{n}{x_A} \\[5pt]
\end{eqnarray}となる。なお、最後の不等式は、(1)を使った。 $A$ を大きくしていくと $x_A$ はいくらでも大きくできるので、 $A_0$ 以上のある正の整数 $A_1$ があって、 $A\gt A_1$ なら最初の式を $0.1$ 未満となるようにできる。
$A\gt A_1$ とする。 $f(x_{A+1})-f(x_A)=(A+1)-A=1$ なので
\begin{eqnarray}
1
&=&
|f(x_{A+1})-f(x_A)| \\[5pt]
&=&
|a_n||x_{A}^n -x_{A+1}^n| \left| 1+ \frac{\left(f(x_{A})-a_n x_{A}^n\right) -\left(f(x_{A+1})-a_n x_{A+1}^n\right)}{a_n x_{A}^n-a_n x_{A+1}^n} \right| \\[5pt]
\end{eqnarray}となり、最後の式の3つ目の絶対値の部分は $0.9$ と $1.1$ の間の値なので、 $|a_n||x_{A}^n -x_{A+1}^n|$ は高々 $2$ である。
\[ g(x)=\sum_{i=0}^k b_i x^i \]とおく。また、係数の絶対値のうち、一番大きいものを $b_{\max}$ とおく。 $A\gt A_1$ のとき、
\begin{eqnarray}
& &
\left| \frac{g(x_{A})-g(x_{A+1})}{a_n x_{A}^n-a_n x_{A+1}^n} \right| \\[5pt]
&\leqq&
\frac{\displaystyle \sum_{i=0}^k |b_i| |x_{A}^i -x_{A+1}^i|}{|a_n| |x_{A}^n-x_{A+1}^n|} \\[5pt]
&\leqq&
\frac{|b_{\max}|}{|a_n|} \sum_{i=0}^k \left| \frac{x_{A}^i -x_{A+1}^i}{x_{A}^n-x_{A+1}^n} \right| \\[5pt]
&\leqq&
\frac{|b_{\max}|}{|a_n|} \cdot \frac{k+1}{x_A} \\[5pt]
\end{eqnarray}となる。ここで、 $|a_n||x_{A}^n -x_{A+1}^n|\leqq 2$ なので、
\begin{eqnarray}
|g(x_{A})-g(x_{A+1})|
&\leqq &
\frac{|b_{\max}|}{|a_n|} \cdot \frac{k+1}{x_A} \cdot |a_n||x_{A}^n -x_{A+1}^n| \\[5pt]
&\leqq &
\frac{|b_{\max}|}{|a_n|} \cdot \frac{k+1}{x_A} \cdot 2 \\[5pt]
\end{eqnarray}となる。 $A$ はいくらでも大きくできるので、最後の式は $1$ よりも小さくできる。仮定より、 $g(x_{A})$, $g(x_{A+1})$ はともに整数で、差が $1$ 未満なので、値は等しい。よって、ある値から先は $g(x)$ は値が変化せず、同じ値を $k+1$ 回以上とることになる。よって、 $g(x)$ は $x$ によらない整数値をとることがわかる。
(2)終
解説
(1)では、 $x$ が十分大きいところでは、 $x^n$ の動きに比べて $x^k$ の動きはすごく小さくなる、ということを言っています。これを使うと、(2)では、 $f(x)$ の変化は $x^n$ の項によるものがほとんどで、他の項の変化はすごく小さくなることが言えます。また、 $g(x)$ も $x^n$ の項に比べるとほとんど変化しません。そのため、ある値より先では $g(x)$ は変化しないことがわかり、定数だということができます。