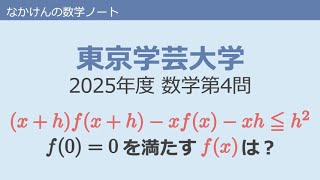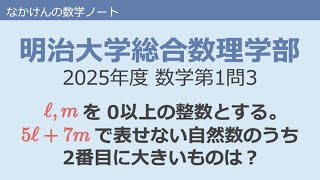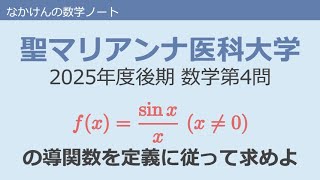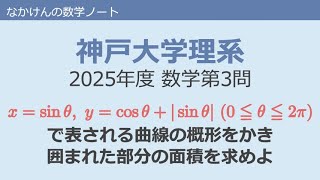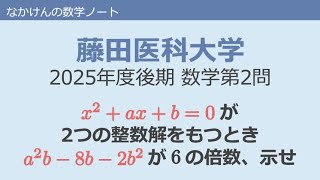【応用】等比数列の極限
ここでは、等比数列を含んだ数列の極限を見ていきます。場合分けが必要な問題を考えます。
等比数列を含んだ数列の極限
$r\ne-1$ という条件は、分母が $0$ になる場合を除いている、ということですね。
具体的に、わかりやすい値を $r$ に代入してみると、 $r=0$ なら分数自体が $0$ となり、 $r=1$ なら $\dfrac{1}{2}$ となります。 $r$ によって、極限値が変わることがわかります。そのため、場合分けが必要だということが予想できます。
そもそも、この分数に含まれている $r^n$ は、 $r$ の値によって極限が変わるのでした。【基本】等比数列の極限で見た通り、
- $r\gt 1$ のときは、正の無限大に発散
- $r=1$ のときは、 $1$ に収束
- $|r|\lt 1$ のときは、 $0$ に収束
- $r\leqq -1$ のときは、振動
$r\gt 1$ の場合は、 $\dfrac{r^n}{1+r^n}$ の分母も分子も正の無限大に発散します。こういう場合は、【標準】等比数列の極限で見たように、影響の大きいもので、分母・分子を割る、という手法が使えることがあります。今の場合、 $r^n$ で割ってみると、\[ \dfrac{1}{\frac{1}{r^n}+1} \]となります。分母にある $\dfrac{1}{r^n}$ は、 $r^n$ が正の無限大に発散するのだから、 $0$ に収束することがわかります。よって、このときは\[ \lim_{n\to\infty} \frac{r^n}{1+r^n}=1 \]となることがわかります。
$r=1$ のときは、 $r^n=1$ なので、\[ \lim_{n\to\infty} \frac{r^n}{1+r^n}=\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2} \]となります。
$|r|\lt 1$ のときは、 $r^n$ は $0$ に収束するため、 $\dfrac{r^n}{1+r^n}$ の分子は $0$ に、分母は $1$ に収束します。よって、\[ \lim_{n\to\infty} \frac{r^n}{1+r^n}=0 \]となります。
$r\ne -1$ なので、残りは $r\lt-1$ の場合ですね。この場合では、 $r^n$ は符号を変えながら、絶対値は限りなく大きくなっていき、振動します。しかし、だからといって、 $\dfrac{r^n}{1+r^n}$ も振動するとは限りません。この場合も、 $r\gt 1$ のときと同様、分母と分子を $r^n$ で割ってみると、\[ \dfrac{1}{\frac{1}{r^n}+1} \]となります。分母にある $\dfrac{1}{r^n}$ の絶対値を考えると、 $|r^n|$ が正の無限大に発散するのだから、 $\dfrac{1}{r^n}$ は $0$ に収束することがわかります。よって、 $r\lt-1$ のときも、 $r\gt 1$ のときと同様に\[ \lim_{n\to\infty} \frac{r^n}{1+r^n}=1 \]となることがわかります。
$r\gt 1$ のときも $r\lt-1$ のときも、 $|r|\gt 1$ とまとめられます。この条件のもとでは、 \[ -\dfrac{1}{|r^n|} \leqq \dfrac{1}{r^n} \leqq \dfrac{1}{|r^n|} \]であり、はさみうちの原理から、 $\dfrac{1}{r^n}\to 0$ となることがわかるわけですね。
以上より、答えをまとめると、
- $|r|\gt 1$ のときは、 $1$ に収束
- $r=1$ のときは、 $\dfrac{1}{2}$ に収束
- $|r|\lt 1$ のときは、 $0$ に収束
$\{r_n\}$ がどのように収束するかで場合分けをし、それぞれの場合で極限を考えなければいけません。
おわりに
ここでは、等比数列 $\{r_n\}$ を含んだ数列の極限を考えました。 $r$ の大きさによって $\{r_n\}$ の収束する状況は異なります。場合分けの必要性に自分で気づいて考えていく必要があります。